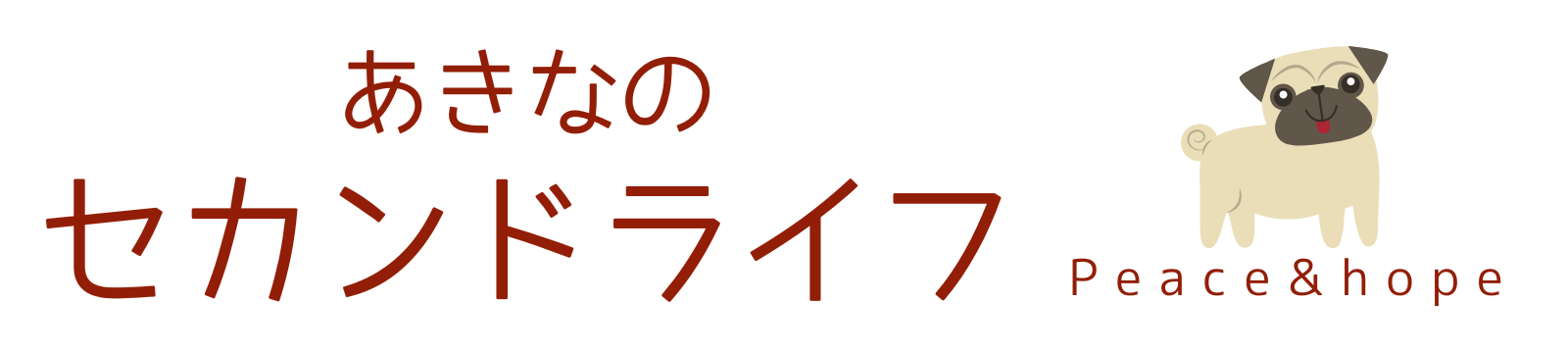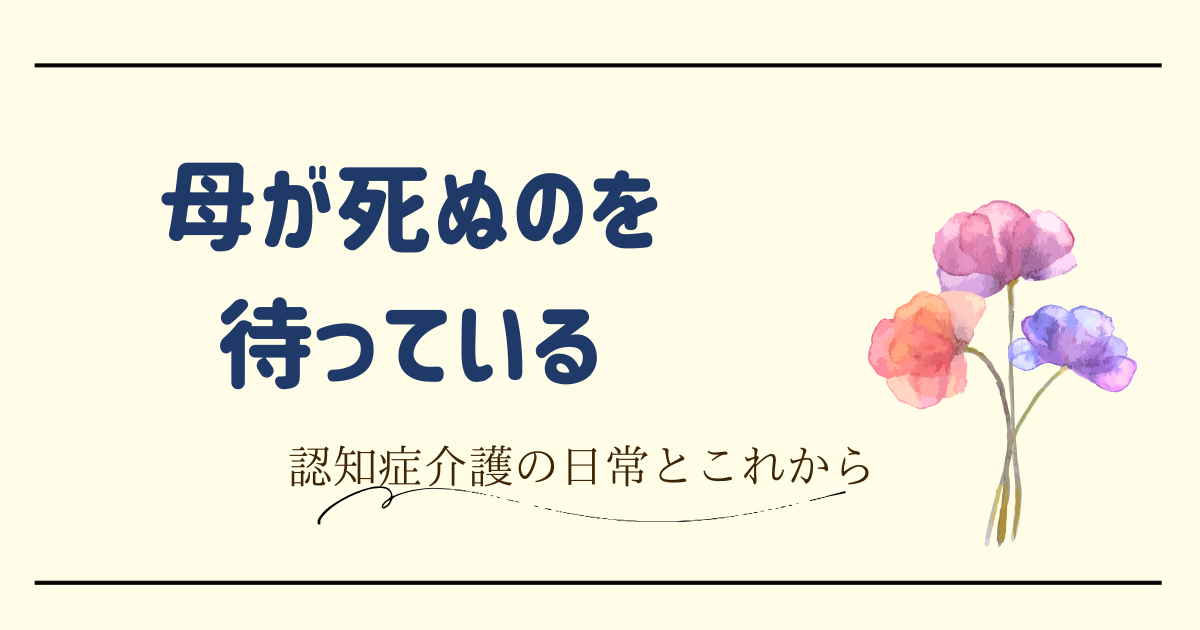わたしは55歳の専業主婦。
母子家庭で育ち、若いころから「母を支えるのは自分の役目だ」と信じて疑わなかった。
十年前に母と同居を始めたが、ゆるやかに認知症の兆候が出てきた。
夫とわたし、そして母の三人暮らし。
子どもたちはすでに独立して家を出ており、家の中はくだらないテレビの音と、夫が飲むストロング缶の音がBGMのようだ。
変わる母の姿
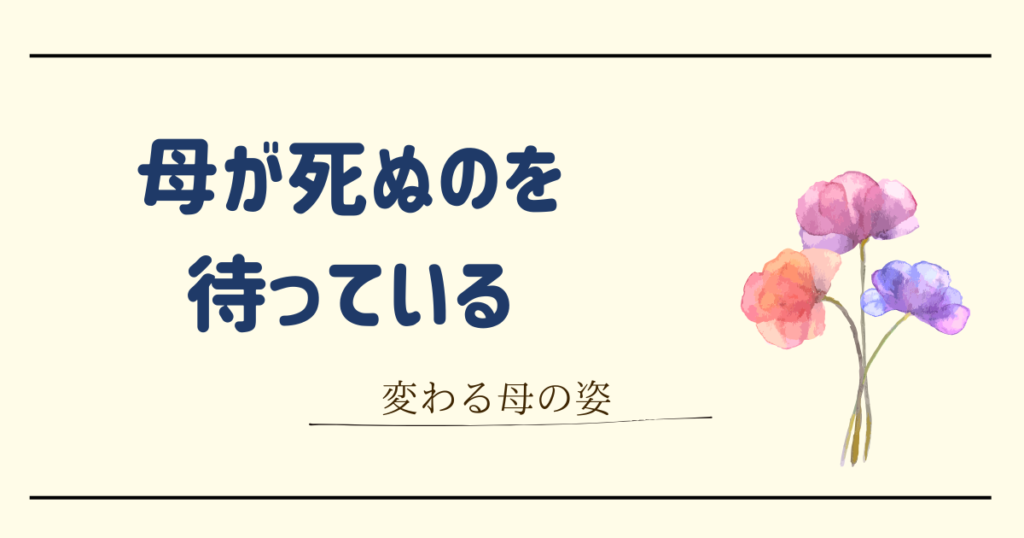
母の認知症は進んでいるが、まだトイレの介助は不要だし、食事も母自身で食べ終えることができる。
ただ、昔から仕事人間だった母がどんどん身の回りのことに無頓着になっていった。
なんとも言えないニオイを放っているのに、本人は自分の体は汚れていないと言い張る。
自分で出来ることは、自分でやり続けて欲しいが、何ごとにも「めんどうくさい」が勝つようだ。
問題が解決したのは、デイサービスに通いそこで入浴するようになってから。
まあそこにたどり着くまで、一筋縄では行かなかったが、入浴問題が解決しても洗濯に手こずる。
「めんどうだねぇ」「私はいいよ、やらなくて」と毎度渋る。
乾燥までやってくれる洗濯機相手に、何がめんどくさいのだろうか。
家庭内での困りごとは、今のところどうにか対応できているだろうが、徘徊し警察に3回お世話になった。
警察のみならず、たまたま通りかかり声をかけてくれた人たちにもお手数をかけてしまった。
ひとりでバスに乗りスーパーで自分の好きなものだけ買ってくる、という母の出来ることも不可能になっていった。
一緒に出かけても、ふと目を離したらどこかに行ってしまい、丈夫な足腰でひたすら歩き続ける。
玄関の鍵を二重にかけ、ドアが開かないようになっていること、母は母なりに理解しており、時折開くかどうか試しにドアと格闘している。
 母
母あんたは私のことが憎いんんだねぇ
母が少し不機嫌そうにつぶやくと、私の胸にはわずかな痛みがよぎる。
若いころ、苦労しながら家計を支えてくれた母の姿を知っているからこそ、今の母が頼りなく映り、胸がざわつくのだ。
死ぬのを待っている・・
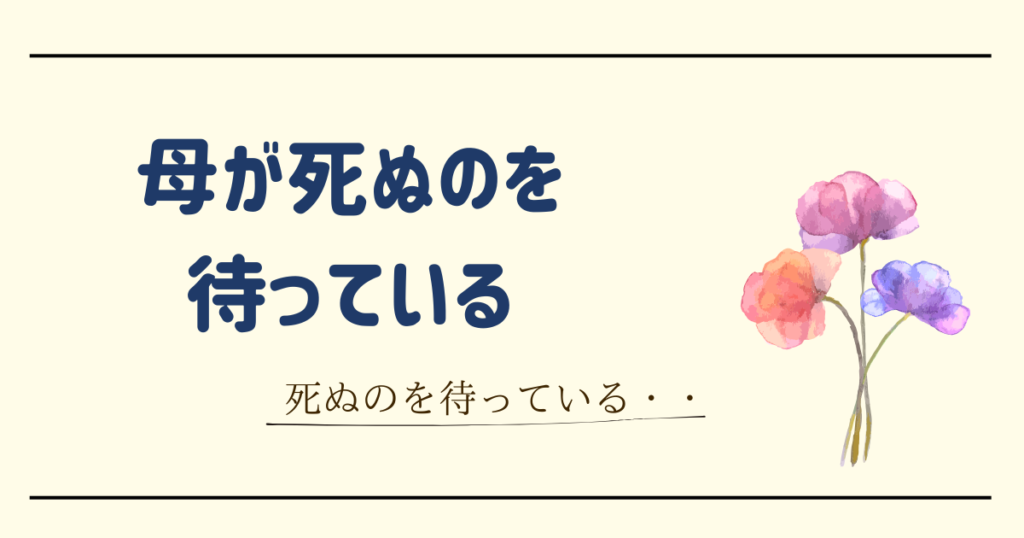
夫は、昔は無口で優しいところもあったはずだが、今では帰宅後の酒が手放せず、些細なことで怒鳴るようになっていた。
酔いが回るたび、「俺には関係ない」「勝手に面倒みてろ」と突き放すように言われる。
わたしが希望した母との同居、そして母が認知症になった現実、だとすれば夫に言われても仕方ないと思いつつ、夜が来るたび胃の奥が重くなる。
酔っ払いの言葉を鵜呑みにするものではないと分かってはいるが、酔ったからこそ夫の深層心理も垣間見えるのだろう。
炊飯器のタイマーを入れていると、夜風が換気扇をパタパタを鳴らし、静寂を揺らした。
そんなとき、ふいに自分の胸に芽生える感情を押さえきれなくなる。
――母が死ぬのを待っている。
その言葉を、ぎゅっと強く握りしめるようにして自分の中で繰り返す。
実際に口には出せないし、出したところで誰に理解されるわけでもない。
それでも、この思いを抱えることに深い罪悪感を覚える。
どうしてこんなふうに感じるようになったのか。
考えてみれば、初めは「母を支えなきゃ」という気持ちしかなかった。
母が記憶を失いつつあっても、昔のように笑顔でいられる時間を作ってあげようと、頑張ってみてはいた。
だが日々の些細な世話が重なり、どこまでも続くトンネルのような暗さが心に張り付いてしまった。
認知症は不治の病だが、それが直接の死因になることはない、とどこかの記事で見かけた。
やはりこのトンネルの長さは、出口を抜けるまで分からないのだろう。
そして多分その先には、夫が認知症になるかもしれないというハードルがある。
ほっと安堵する間もなく次の障壁が始まると思うと、絶望に近い感情さえ湧いてしまう。
やがて矛先は自分へ
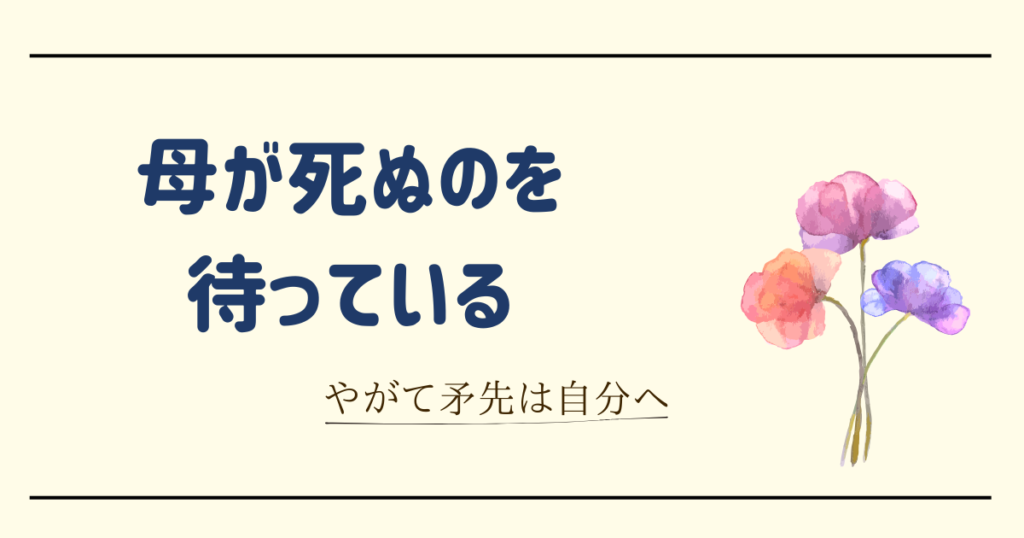
そして、いちばん恐ろしいのは、自分も将来認知症になるかもしれないということだ。
もしそうなれば、わたしの子どもたちが今の自分と同じように「母が死ぬのを待っている」と思うのだろうか。
その想像が、心に冷たい痛みを落とす。
血のつながる親子は、夫婦と違って「他人」には戻れない。
夫との関係なら、どんなに難しくても離婚や別居という選択肢がゼロではない。
けれど、親子はたとえ心が離れても、血の縁からは逃れられない。
絆か呪縛か、わたしにはもうわからなくなっていた。
また明日がやってくる。
この繰り返しがいずれ、夫の介護、そして自分の最期へとつながっていくかもしれない――
そんな思いが、小さな生活音の中でやるせなく渦を巻いていた。
いずれ、わたしが死ぬのを家族に待たれるようになるのだろうか。
認識の違い

母はデイサービスに通うようになってからは、むしろ楽しそうに過ごしていることが多い。
「今日もお年寄りの方たちとお話しするのよ。私がちゃんと面倒を見てあげないと」
そう言って、はりきった様子で出かけていく母を見送るとき、いつも心がざわつく。
母はもともと介護福祉士として働いていた。
だからなのか、自分が“お世話になる”立場なのに、デイサービスに行けばまるで“スタッフ”のように振る舞っているのだと、施設の人も苦笑まじりに話していた。
「ま、お母さんは職業柄、誰かの世話を焼くことで生きがいを感じるんでしょうね。そこまで困ることはないですよ」
電話越しにデイサービスの職員がそう言ってくれると、どこかほっとする半面、くすぶる感情もある。
実際、母はお風呂の介助など、本当はされる側なのに、時々ほかの利用者さんの動向を気にして「誰か手伝いましょうか」なんて声をかけているという。
スタッフさんはときに困りつつも、「うまく母の気持ちを尊重してくださっている」とは聞いている。
身体の衰えもさほど深刻ではないし、母がこうして積極的に外へ出ることで気が紛れているのは良いことだろう。
だけど、わたしは胸の奥底で、うまく言い表せない違和感に苛まれていた。
母は帰宅すると、施設での出来事を愉しげに話してくる。
「今日はね、足の悪い人をリハビリ室に連れていったのよ」「私が何でもやってあげないといけないから」と、ちょっと誇らしげな口調だ。
だけど――本当はあんたが世話される立場なのよ、と突っ込みたくなる。
しかし、自分を“介護される人”ではなく、“介護する人”と認識しているうちは、母にとってもそのほうが幸せなのかもしれない。
かつて現場で活躍していたプライドを、最後まで手放したくないのだろう。
まだ身体も動くし、認知症もさほど重くないのに、どうしてこんなに「母がいないと楽になるのに」と思ってしまうのか、自分でもわからない。
言いかえれば、介護というほど大変な場面はそこまで多くないはずだ。
人として最低だと思いながらも、そう感じる瞬間が日に日に増えているのは事実だ。
もし母がもっと重い要介護状態になったら、自分の心はどこまで荒んでしまうのだろう――そんな怖さもある。
これからも同じように

日々の静かな繰り返しの果てには、いつか別れの時が訪れる――そのことだけが唯一の確定事項だ。
時計の針はしっかり進んでいて、わたしの人生を少しずつすり減らしていく。
そう自覚しながらも、歯車から降りる術がわからない。
ほんの少しだけ、母が楽しそうにしている顔を見て、「これでいいのだ」と自分をごまかすことができる程度だ。
まるで緩慢な流砂に浸かっているような、この日々。
わたしは、そこにわずかな意地で足を踏ん張りながら、自分の人生がさらさらと消費されていくのを見送っているのだった。
また思考が負のスパイラルに突入したようだ。
あれから何日が経ったのだろう。
外は冬から春へ変わろうとしているのに、わたしの暮らしはどこか薄暗く、どこかあいまいなままだ。
母は相変わらずデイサービスへ出かけては、介護福祉士だった頃の癖で、周囲の利用者さんたちを“世話しているつもり”で過ごしているらしい。
その話を聞くたび、認知症であることを忘れている母がほほえましくもあり、どこか取り残されたような気分にもなる。
夫は酒を飲み、時々は文句を言うか、もしくは何も言わずに眠りこける。
わたしは朝晩の家事をこなしながら、同じように過ぎ去る一日一日をやり過ごす。
親や夫の将来がどうなるか、想像してみることもある。
でも、あれこれ考えてもいつも空虚に行き着くだけだ。
なにもしないということ

母がこの先どうなるのか知ったこっちゃない――そう自分に言い聞かせるようになったのは最近のことだ。
冷たい思考だとわかっているけれど、それが今のわたしには唯一の防衛手段のような気がする。
夫との老後だって、話し合ったところでどうにかなるはずもない。
互いに深く立ち入れないまま、ただ同じ家にいるだけの関係がこのまま続き老いていくのかもしれない。
どうやったらネガティブな感情から逃れられるのか、答えは出ない。
むしろ、これまでなんとかしようと空回りしてきた自分を思えば、急いで結論を出しても同じ結果に落ち着くだけだろうという予感がある。
そこで思いきって、何も決めないことにした。
流れに身を任せると選んだのだ。
翌朝、母はいつもどおりデイサービスの迎えを待つ。
ピンポンが鳴ると、ちょっと誇らしげに出かけていく。
まるでこれから職場へ行くかのように、わずかに背筋を伸ばして。
わたしはそれを見送ったあと、台所のテーブルに腰を下ろして、安堵のため息をつく。
母がいない空間で飲むコーヒーは、ほんの少しだけ美味しさが増すように感じる。
洗濯物を干して、昼食を簡単に済ませる。
テレビでは新しいニュースが流れているが、ほとんど耳には入らない。
何かを決断して変わることを夢見ていた頃もあったけれど、今はそれさえ空回りに思える。
だからわたしは、あえてこの宙ぶらりんのままを選んだ。
なにかあれば、そのとき動けばいい。
夕刻になれば母が帰ってくる。
デイサービスでの“活躍”をうれしそうに報告し、「私がいないとあの人たちも大変なのよ」なんて言う。
わたしは相槌を打ちながら、「それもいいんじゃないか」と思うようになった。
母の思い込みが続く限りは、母の心に張り合いがあるのだろう。
それに今さら「あなたは利用者の側なんだよ」なんて突きつけても、母も戸惑うだけだ。
日が沈んで、夫がやがて帰宅し、酒を飲む。
わたしは相変わらず「おかえり」と声をかけるけれど、あちらからは「……ん」という返事がわずかに戻るだけ。
歯車が噛み合わない生活が、今日も延々と続いていく。
だけど、わたしはもうそれを変えようとは思わない。
そう決めたのだ。
もしかすると、いずれこの選択を深く後悔する日が来るかもしれない。
でも、何をどう決断しても、後悔する可能性は拭えない。
それなら今はただ、こうして淡々と暮らしを回していくことしかできないのだ。
いつか遠い未来、たとえわずかな時間でも「あのときはあのときで、懐かしいもんだったわね」と、振り返る日は来るのだろう。
そのときのわたしがどんな心境になるのか、想像する余裕はまだない。
日々が灰色のようにすすけていく一方で、わずかな色合いが混ざる瞬間もきっとあるはずだ。
母が何か奇妙な話をしたり、夫がほんの少しだけ笑ってみせたり……。
かすかな光を探しながら、わたしはあえて何も決めない自分に言い聞かせる。
「いまはただ、流れに任せていよう」

こうして、わたしの停滞した日常は、明日もまた続いていく――
いつか、わたしの未来が振り返るであろう今の時間を、わたしは静かに受けとめているのだ。
買い置きしてある夫のストロング缶を、一本拝借する。
プルタブを開けアルコールでモヤモヤを誤魔化し、母と夫の帰りを待つ。
夫がお酒を辞めない理由を体感しながら、炊飯ボタンを押す。
認知症と酔っ払いの空間に、またひとり酔っ払いが増えただけだ。
ただ、それだけのこと・・・・